思うに、自由思想家が出現する前の時でも、ヴェーダの世界観がインド全土を絶対的に支配していたということはないのではないでしょうか。ヴェーダ時代に他にどんな思想があったとしても、記録を残せたのはバラモンだけでしょう。だから実際は多くの異なった思想が世間にはあっただろうということは容易に想像できます。
仏教にはいくつもの流れがあって、それらが混じり合っているところが少なくないので、これが仏教だというのは難しいというか、不可能に近いのですが、大きく大乗仏教と上座部仏教に分けて、その特徴おおざっぱにを見てみます。
大乗思想では釈迦は二元論的考えや、座禅による精神的原理との同化をもって煩悩消滅・解脱とすることに疑問を持ったとします。また、苦行も否定したといいます。釈迦にとって問題だったのはこの世界に生・病・老・死という「苦」をもたらしている原因だったので、彼はその原因を「分別智」にあると覚り、「無分別智」に至ることこそ解脱と悟ったといいます。
しかし、釈迦本来の思想は南伝仏教・上座部仏教に残されていると思われます。上座部仏教によると釈迦の根思想は「諸行無常、諸法無我、涅槃寂静」ということです。それをどう解釈するかが彼らの思想だったようです。宗教的態度としては学習、戒律、瞑想を重んじるなど、苦行というほどではないが、厳格な求道者というところでしょう。
「諸行無常」とは釈迦死後のインド仏教にいう①一切のものは刹那生滅のものであり、一切のものは苦しみである」ということでしょう。これは大乗でも同じです。
「諸法無我」は大乗では往還自在の「空」になるのでしょうが、本来は「この世のすべては実体のないものである」ということだけでしょう。しかし、実体はなくても「法」はあるわけです。「法」からは「根本原質」のにおいがします。サーンキャ哲学の物質的原理「根本原質」が実際は「心的(霊的)原理」であったように、「法」もまた「心的原理」です。
「涅槃寂静」は「実体の無いものをあると思う」煩悩の火が吹き消された状態をいうのでしょう。結果、「純粋精神」のようなものに至るのです。「諸行無常」と「諸法無我」を物質的原理とすれば、これは精神的原理です。この解脱への一方通行が釈迦本来の思想でしょうが、大乗ではこの境地に様々な差異をつけて、完全解脱状態を往還自由な(菩薩)状態より低く見ているようです。
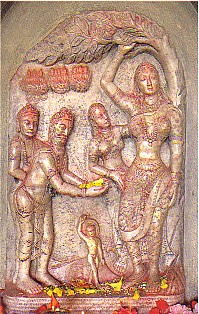
有名な「天上天下唯我独尊」という釈迦誕生の言葉はもちろん創作ですが、釈迦の魂観を良く表す言葉だと思われます。おそらく彼の考えではすべてのアートマン・自我はすべて同じ力を持っているものなのでしょう。そして同じように自尊心が高いのです。そしてまた究極的には一体のものです。