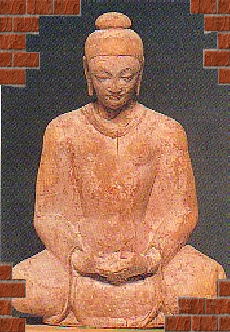
仏教的人間観からいえば、魂には自分を犠牲にする精神も自分だけ得しようとする精神も本来ないものです。純粋無垢の魂は「無」なのですから。魂の発達段階によって自分と他者との一体感が強いのか、それとも他者への憎悪が強いのかという違いができてくるのではないでしょうか。みな状況の産物です。自己の本質は「無(無我)」なのです。愛の本質は自他の区別のない「無(無差別愛)」なのです。実存主義者の自己犠牲愛の源泉もこれですが、社会正義に限定されてしまっているのです。よく聞く話ですが、子供が水におぼれた友達を助けようとして自分も死んでしまったとか、自分の方が死んでしまったとかいうことがあります。子供のころには自分の危険や実力を忘れて助けに走るほどの友情を持っているのです。しかし、まだ自我が未発達だからだといえるでしょう。自我の発達した大人が「自己犠牲」云々を言い出すのは、そうした子供の時代の純粋さに帰りたいということかもしれません。そうした純粋さを取り戻すためには大人の自我を放棄しなければなりません。しかし凡人が自我を放棄するには俗世を離れた厳しい修行が必要です。そんな修行はしたくないというのが大方の人情です。その上、修行の結果人のために犠牲になって自分を消滅させる人間になるわけで、普通ならあまりありがたくないと思うのではではありませんか。しかしまた、そういう人間になりたい(無に帰りたい)というのも魂の真情です。そこに自己犠牲への尊敬も生まれるのです。
このように宗教は本来魂の本性に根ざすものです。宗教は麻薬であり現実逃避に過ぎないと批判するのは青春の特権ですが、釈迦やキリスト個人の精神をそれによって批判するのは間違いです。しかし、宗教を、現在の世界精神においては逃避的、幼児的依存心という批判は免れません。