釈迦の思想がなぜ世界宗教となりえたのか。その答えはユダヤ教から出たキリスト教やイスラム教が世界宗教となりえたのと同じ、平等主義によるものだと考えられます。バラモンの差別主義に対抗したのは釈迦だけではなく、唯物論やジャイナ教のような物心二元論もあります。同じ平等主義でもそれらが世界宗教とならなかったのは彼らが知的で自己肯定的であって、すなわち差別的だったからではないでしょうか。人々が宗教に求めるのが完全な自己否定であったからでしょう。つまり大衆はみんな反知的であり、自分自身、そして人間が嫌いなわけです。釈迦の理論は反知的で自己否定的でした。人間を信じ、自己肯定的で、自分には世の中を変える力があるという青春の情熱との違いは大きく、青春の魂には許すべからざること、理解不可能なことといえます。
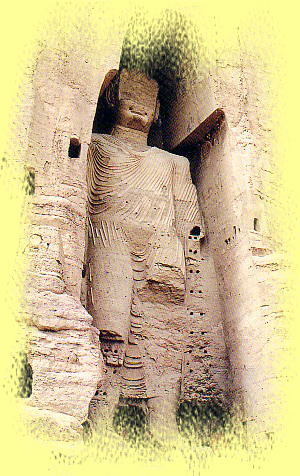
仏教成立その後
釈迦の思想(を元に生まれた宗教)は、その死後百年ほどで金銭授受の戒律をめぐって論争が起こったということです。いわゆる大衆部の成立です。大衆化、つまり修行解脱よりも、良く言えば大衆済度という、商売大事の人たちの道具となり始めたようです。こうして大衆化の進行するとともに、釈迦は非人格化され、大衆からは超越的存在として祭られるようになって行きます。そのころ現れたマウリヤ朝のアショーカ王の帰依によって仏教は勢力を拡大し、その傾向に拍車がかかったようです。大衆仏教は、宗教者のたくましい想像力によって分裂していき、(つまり個性化です、平和は人々を分裂させるものです。)分裂の金字塔として成立したのが、さまざまな仏や菩薩の伝説物語である経典だということができます。経典には後に成立する大乗仏教の阿弥陀経や無量寿経、法華経などのように、うそも方便といって、人々を泣かせる利他の美しい物語が書かれているわけです。華厳経という壮大華麗な仏法世界の物語もあります。こうなるともう釈迦の『無』思想とはいえません。
比較的平和な王朝時代は仏教の貴族的大衆化を進めたでしょう。しかし、釈迦の死後五百年たったころ、新たな北方騎馬民族のインド侵攻が始まるなどがあったのでしょう、インドは阿鼻叫喚の地獄と化します。明日を知れない身となっては、もはや解脱の聖者を崇拝していくなどという悠長なことは言っていられなくなります。単なる超越的神秘的な神仏でなく、力強い救いの神を求めるようになります。その要請に応えるために宗教も変革していったのです。バラモン教は、クリシュナのような絶対的な力を持つ神を仕立てて、ヒンズー教化していきます。それに対抗するためにも(本当はどちらが先かは分かりませんが、おそらく相乗的にでしょう)仏教も大衆救済の宗教力をヒンズー的に拡大しなくてはなりませんでした。釈迦や弟子たちは巨大神化されるとともにその身を捨てて(キリスト教と同じ論理ですね)大衆を救う愛の化身となり、そのための物語が次々創作されていき、大乗仏教の成立となりました。。
しかし、大乗経典には般若経のように『無』に関するものも、竜樹の「中論」のように認識や自己の成立に対する理論思索をしたものもあって釈迦の教えを捨てたわけではありません。ただ釈迦の『無』は『空』に変身しました。紀元前後に出現した般若経の出自はわからないらしいですが、釈迦においては解脱の一方通行だった『無』が、この世と往還自由な『空』に変わったのはこの経典からだといいます。『空』の思想を大成したといわれる竜樹という大乗の大思想家によると、仏教とは世俗の教えと真理の教えの二つで成り立っているのであって、片方だけ理解していては仏教を理解できないということらしいのです。この仏教的理論武装として考案されたのが般若心経の『空』だということができるでしょう。人を救うことによって自分も救われるという大乗仏教の確立です。彼の言う『空』とは「色即是空」というすべての消滅するところと「空即是色」というすべてが生まれるところ、すなわち「量子論的無」を思わせるものです。『空』とは釈迦が言及しなかった世界の本質、絶対的実在だということもできるでしょう。「無常」ということは解脱したものも『無』にとどまることなくまた再生するというわけです。いったん解脱した釈迦もまたこの世界に戻ってくると考えることができるのです。だから大乗仏教は解脱が目標ではなく、世俗的な世界、民衆の救済ための菩薩道を行いながら真理の境地、すなわち『無』に生きるということなのでしょう。だから苦行を否定し、ただ教義を理解することによっても悟りを開くことができるというようなことも言い出すのでしょう。そうなると厳しい修行など否定するようになるのが人の常というものでしょう。日本的大乗仏教では読経をしたり聞いたりするだけでも極楽へいけるというわけでなんとも楽なことです。