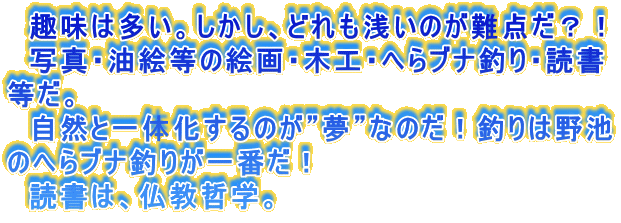
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���R���D���@���R�������������I�v �@�@�@�@�@�@�@Home Page ��
It links it to
�@"I want to live a life that works together to
creates with nature and enjoys it."
�@�@
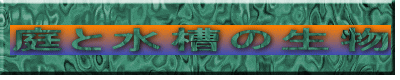 �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�g�߂ȐA�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 |
 |
�F�ǂ̑��Ԃ��A���C�Ȃ��炢�Ă���B�����A���������̂͂Ȃ��B
 �@�Ȃ̕�́A�V���Ďs���̘V�l�z�[���ɗa����ꂽ�B �@�Ȃ́A���̕��Ɨ����̊Ō�����Ȃ���̓��X�����炭�������B �@��̕a���ɁA�Ȃ��������Ԃ́A���������k�������Ȃ���A���^�ȉԂ𒅂����B |
�@���ɂ́A�Y����Ȃ��ԂƂȂ����B �@�`��́A �@�ȂƏ����ƁE�E�A�V�l�z�[���ɋΖ����鎄�̖��ɕ�����āA�Â��ɐ������B �@�ƂĂ��Â��ȁh���h�ł������B  |
�B ���i����܁j�@�@�@�@�@�@�@Link�@
| ���́A�B�����D�����B����ŋC�ɓ��������̂�����A���ꂪ���ɂƂ��ēK���ȉ��i�Ȃ�� �w���������Ȃ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�ό��n�⎛�@�ɍs���ƁA�����A�꓁���̐��i��̔����Ă���X��T�����ƂɂȂ�B �������A�C�i�̂���ʗ����̂��̂��Ȃ��Ȃ������B �@���́A�B���ƕs�������́A�����߂�����ɁA���͎䂩���̂ł��B �@�ۂ��Ǝ������ϔY�̌ł܂�̂��Ƃ��A�������܂悢�����Ă����B ���ȉ䂪�g���v���A���̂������E�E�E�A �S�̓������������悤�Ȗʗ����́E�E�E�A����Ȋ���̒B���l���D�����B |
�B���Ǝ��ӂ̕����j�T��
| �S�V�U�N | �@�����ŁA���a�i�`542�j���a�B�e�a�������m�ɋ�����m�S�B�k鰂ܑ̌�R�ŏC�ƁB �T�O��ɗ��z�ł���O���i�ٸ۰�ނ�ʂ��đ����̌o�T���g���ė��āA�����Œ�����ɖ|�j����A�u�ϖ��ʎ��o�v���������y�̋����ɋA���A��o���Ă����Ă�B�@ |
| �S87�N | �d���܂��(�`593�j�B�B���̓�c�B�d�����o���n�ǂ��B�ݖ@��@�A�g�Ŗ����ʂ�����A���g�����̋`�𗧂B |
| �T�Q�O�N | �@�B���i��V���̍���������̑�O���q�ŕ��(�����)�Ƃ������O�j���ނ���L���ȍL�B�ɏ㗤����B�����ŏC�s�B |
| �T�R�W�N | �@�S�ρi�������j��蕧���i�����ƌo�_�j���`�i����ɂ͂T�T�Q�N�j�B�V���t�q���i�����j���܂���i538�`597�j�B |
| �T�U�Q�N | �@����i�C�߁j�A�V���ɂ��ŖS�B�����ŁA���^�i�ǂ����Ⴍ�`645�j���a�B�e�a�������m�ɋ�����m�T�B�����k���̕���͕��@�������ߌ��Ȕ��Q���s�����B ���̎���ɂP�S�ŕ���ɓ���B���Ϗ@�ɋA�˂��Ă������A���鎛�œ��a�̔蕶��ǂ�ŋ����Ռ����A�������͂̓��𓊂��̂Ăđ��͂̋����ɋA�˂����B�����肱�̎��E�������̈ڂ��t�́u��y�_���v����Ƃ��āA�O�������ɓ���B���t80�̂Ƃ��ɑP��������B |
| 593�N | �d�@�v(487�`593�j�B�B���̓�c�B |
| �U�O�O�N | �@��P���@�g�h�� |
| �U�O�Q�N | �@�����O��(�ݽ�دČ�̔ʎ�S�o�𒆍���ɖ|��)�����E���z�ɐ��܂��B |
| 606�N | �@�m ��@�v�B�@�B���̎O�c�B�B���̗����̐[��������B�@�M�S���@�`���F��������A�Ҍ������i�䂢�����j�B |
| �U�P�Q�N | �@�������q���A�u�O�o�`��i��題o�`���F611�E�ۖ��o�`���F613�A�@�،o�`���F615�j�v�����B���̔N�����O���A���Z�Ƌ��ɗ��z���璷���Ɉڂ�B�P�V�ˁB�@�@�@�@�@�@ |
| 651�N | �@���M�v(579�`651�j�B�@�B����l�c�B |
| �U�T�Q�N | �@���������{�i�i�ɘa�C���ق킯�݂̂��Ǝn�ߌܒ��j�n���B���̔N�J�X�~��A�l�{�E�c���E�Ɖ����Q�傫���B |
| 674�N | �@�O�E�@�v(601�`�j�B�@�B����ܑc�B |
| 713�N | �@�d�\�i638�`713�j�v�B�@�B����Z�c�B |
| �P�Q�R�S�N | �@���{�B���@�̑m�A�lj_����(��ޮ�)�������T�t�ɓ��傷��B�i�@�h���z���������ꂽ���ƂɂȂ�j ���̔N�A�e�a���O�͖������i���������q���j�Ő��@���s�����Ƃ����B�܂��A�����R1700���i�{�茧�Ǝ��������̌����j�������N�ł�����B |
�W�߂��B���Ȃ�
 |
 |
|||||||||||
 |
 |
|||||||||||
 |
 |
|||||||||||
 |
 |
|||||||||||
 ��q�̌d�́A�^�������߂邽�߂ɁA �u��q�ɂ��Ă���I�v�ƁA���肷����f��ꂽ�B �����肢���邪�A��͂蓚���͓����B �ᒆ�ɍ����đ҂��A��˂����Ă���Ȃ��B �@�����Ŏ���̘r��ؒf���āA���ӂ̒��� �������Ƃ����B���u�d�f�]�v�̓`���� �@�^�����ے�����h�B���h�T�t�B�Ђ�������T�ɖ� �����āA���̎p�ɂȂ����Ƃ������̂ł���B �@�����͂Ƃ������A���́h�B���h�����D���Ȃ̂��B �@���̂��̂͗���������B ����́A�������ɎQ�q�����Ƃ��ɋC�ɓ����āA �F�l����s�����̂�������Ď�ɓ��ꂽ�B |
 |
|||||||||||
 |
 |
|||||||||||
| �@���ߊω��́A�������ďՓ����������B | �@���ߊω��́A�ٍ��V�̉��g���ƕ������B �@��e�ɐ��������������A�c��ɐN���̋ꂵ�݂������u���ł��Ȃ����t�v�𓊂�������ꂽ�B �@�Ȃɂ͊��ӂ��邱�Ƃ������B���̑��A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ�����������B �@�����́A���Ɉ̑�ȑ��݂��E�E�ƁA�z���B |
|||||||||||
| ���B���̂����@�@�������ā@�u���{���_�ʋ`�v�@��蔲�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Link�@ |
||||||||||||
�T��̋���ƒB���̐^�������A�T�Ƃ������t�͞����i�ڂj��Dhyana�������u�T���i����ȁj�v�̖��ł����āA�×��i�������j�A�ґz�i�߂������j�̈Ӗ��ł���B |
||||||||||||
| |
||||||||||||
�@�B�����`�̑T�����T�� �@�����@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�@�������ā@�u�T�Ɨz���w�v�@��蔲���@�@�R�P�S��
|
||||||||||||


